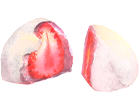2024年11月29日
オープン
場
所
イオンモール
登美ヶ丘1階
ニッポンの銘菓を
集めました

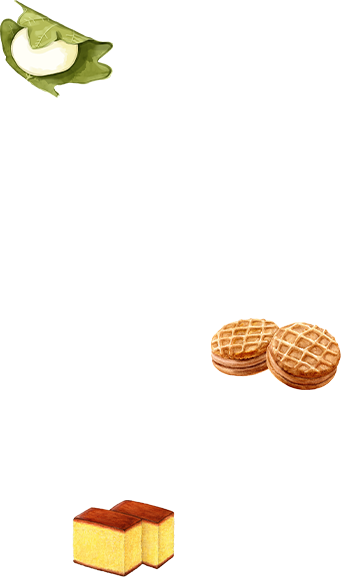
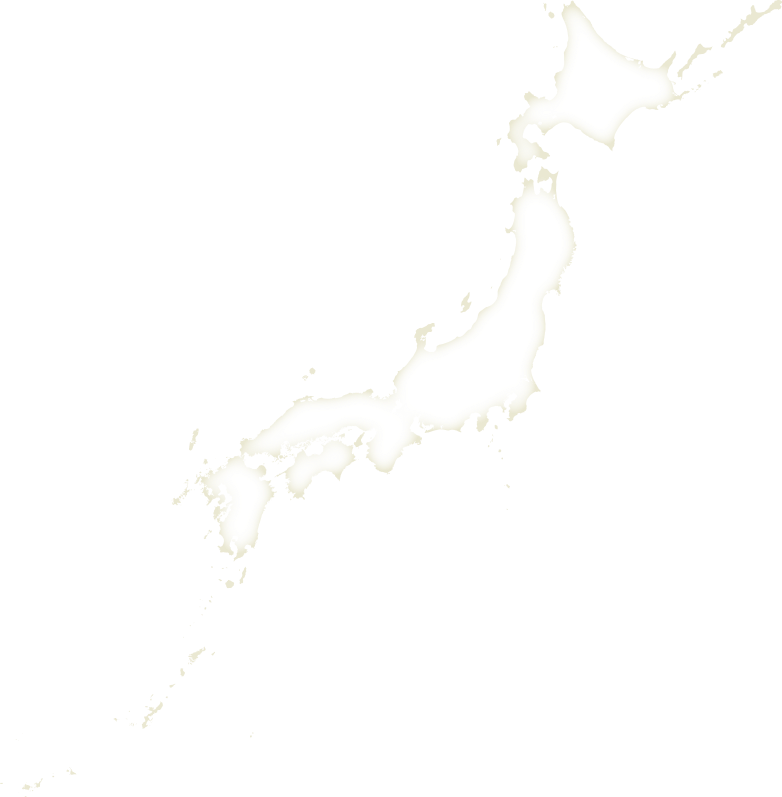
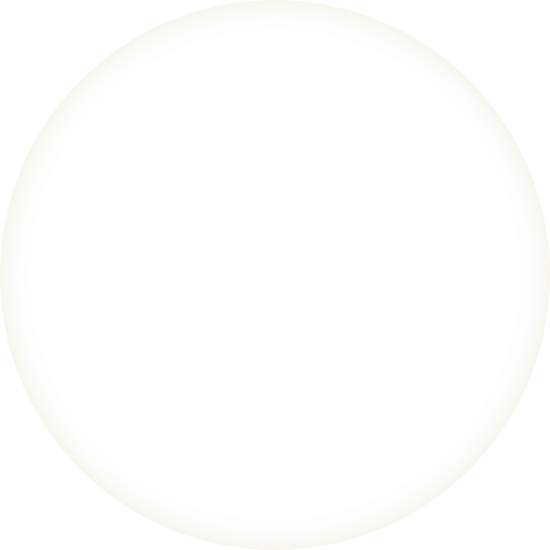
当店について
当店は日本全国の銘菓をバイヤーが厳選して
集めたセレクトショップです。
ニッポンの伝統や歴史、
文化を表現した地域にゆかりあるお菓子を
気軽に手に取ってもらい、
各地域の魅力や四季折々の素敵な銘菓を
楽しんで頂ければと思います。

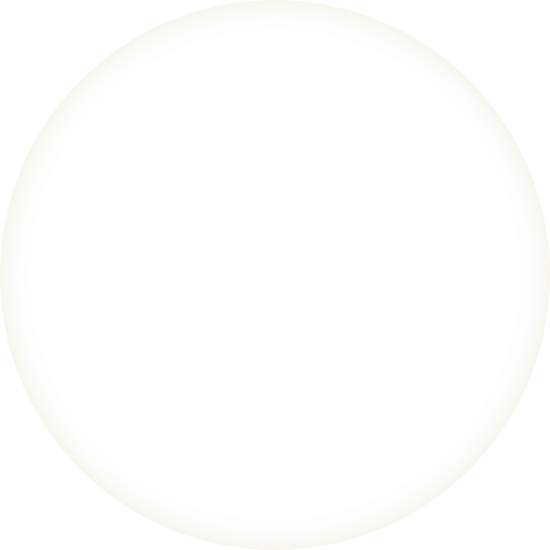
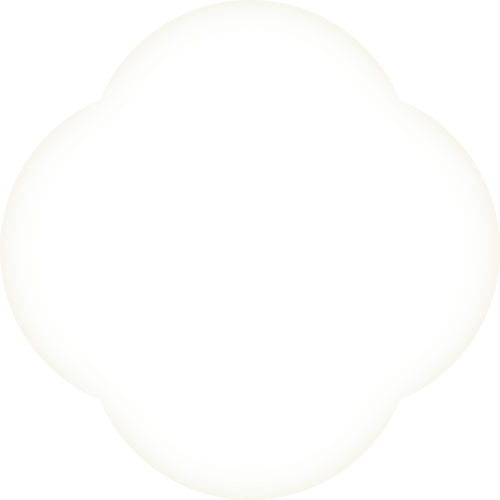
商品ラインナップ
羊羹、最中、きんつば、饅頭、大福、餅、団子、どら焼き、カステラ、琥珀糖、おかき、煎餅、
豆菓子、飴、グミ、ゼリー、
チョコレート、
ポテトチップス、かりんとう、ドーナツ、
クッキー、焼菓子、など
北は北海道から南は沖縄まで47都道府県の魅力が詰まった銘菓を取り揃えました。
-

千代乃舎竹村|奈良県
奈良饅頭
-

回進堂|岩手県
岩谷堂羊羹
-

さいとう製菓|岩手県
かもめの玉子
-

青柳総本家|愛知県
ひとくちういろう
-

房洋堂|千葉県
花菜っ娘
-

小宮せんべい本舗|埼玉県
草加せんべい
-

虎屋本舗|広島県
元祖名物 虎焼
-

南国製菓|高知県
巾着 塩けんぴ
-

奈良祥樂|奈良県
らほつ饅頭
-

島ごころ|広島県
レモンケーキ
-

琉宮|沖縄県
サーターアンダギー
-

沖縄南風堂|沖縄県
雪塩ちんすこう
その他、日本全国500種類のラインナップを
取り揃えております。ぜひお立ち寄りください。

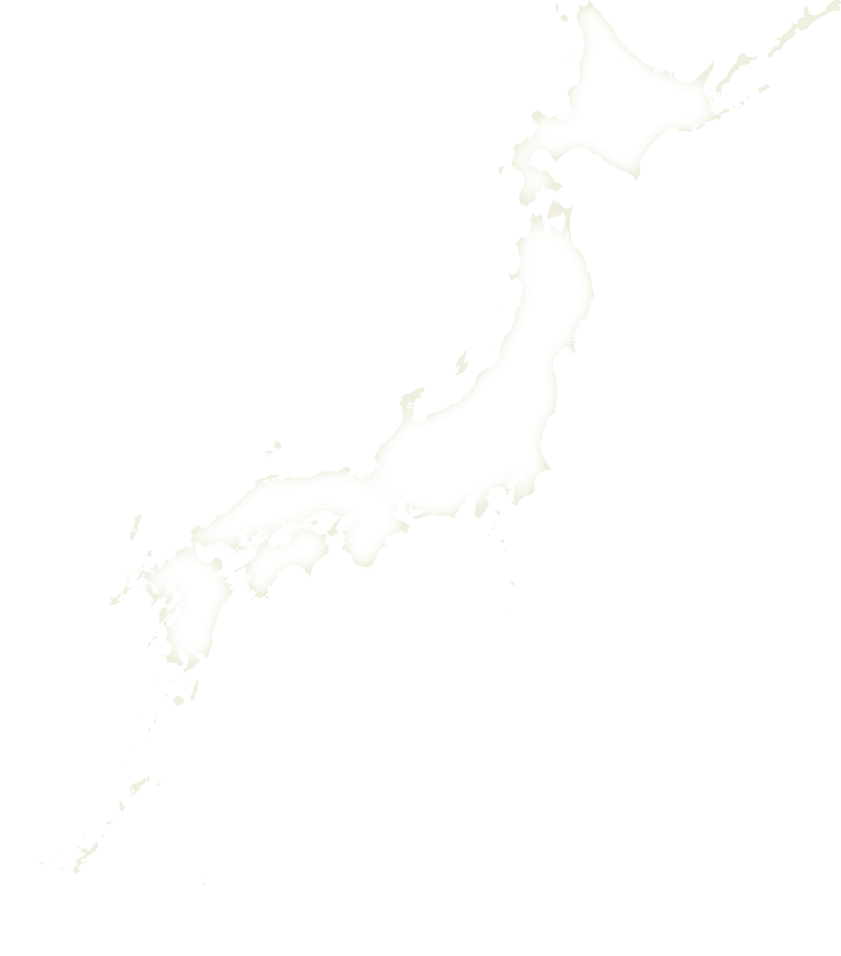
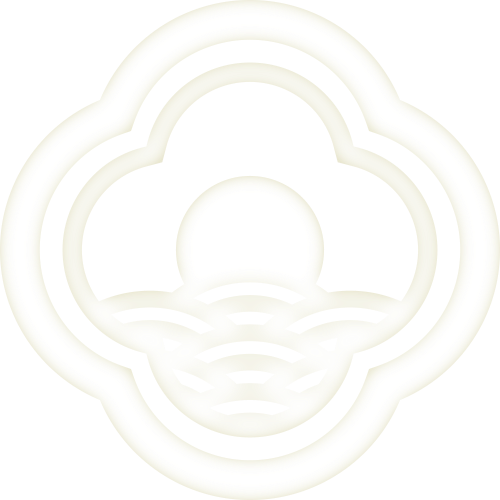
私たちの想い
ニッポンの銘菓は代々受け継がれる
歴史溢れる逸品です。
日本が誇る技術や伝統、文化、地域の魅力が
詰まっています。
そんな各地域の中で根差してきた銘菓を
より多くの人に知ってほしい。
そして、日本を感じてほしい。


海外の技術が発展していく中で、
日本人の日常の中にも海外製品や食品が
溢れています。
今こそ原点回帰として、
日本が日本であり続けるために、
私たちは日本の素晴らしさを
銘菓を通じて伝えていきます。

店舗情報
地域ゆかりの百貨店
イオンモール奈良登美ヶ丘店
- 住所
-
〒630-0115
奈良県生駒市鹿畑町3027
イオンモール登美ヶ丘 1階 - 営業時間
- 9:00 ~ 21:00